
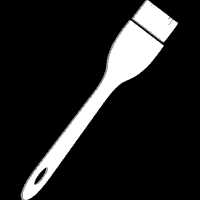
Now Loading...
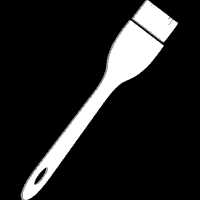
Now Loading...

第4回全国中学生アートの甲子園福井WEB展
実行委員会実行委員長 牧井 正人
第4回全国中学生アートの甲子園福井WEB展の開催にあたり、実行委員会を代表して、ごあいさつを申し上げます。このたびは、本展覧会にご参加いただき、またWEB展をご覧いただき、誠にありがとうございます。
本大会は、全国中学校美術部員の選抜展覧会です。ただし、地区大会を継続的に開催している、埼玉県朝霞班 埼玉県川越市 千葉県印旛郡市 愛知県知立市 福井県 大阪府堺市 奈良市 沖縄県の8地区の先生方と実行委員会を結成し、開催に至りました。まずもって、参加いただきました中学生の皆さん、素晴らしい作品をありがとう。そして、その橋渡しをしていただきました各中学校美術部顧問先生方、各地区の先生方、本当にありがとうございました。
全国8地区から、中学生の「今の思い」が表現された154点の作品が、このWEBページに集まりました。いずれの作品も、各地区展で審査され、優秀な成績を残した作品ばかりです。今回は、作品を展示する会場の確保が難しかったこと、作品を輸送する経費の高騰などの理由から、実際に実物を展示する展覧会の開催はできませんでした。大変残念ですが、「WEB展でもいいので開催してほしい」との思いを受け止めて、昨年夏から準備してきました。しかし、このような形でも継続できたことは、大きな意義があるのではないかと思っています。
そもそも、なぜこのような中学校美術部の展覧会「アートの甲子園」を福井県が事務局として開催することになったのか、少しお話しします。
2021年夏、これまで14回開催されてきた「全国中学生アートクラブグランプリin SAKAI」(事務局 大阪府堺市)がコロナ禍の中、急遽中止となってしまいました。堺は、美術部の聖地でした。高校球児で言えば、夏の甲子園大会が急になくなってしまったようなものです。美術部の全国大会を目指してきた中学生は、このことにより大きな目標を失ったのです。
福井県では、2010年度より「ふくい中学生アートリンピック展」を開催してきましたが、この全国大会を目標にしてこれまで続けてきました。中学生に目標や夢を持たせることのできる全国大会に向けて、美術部員は私たちの期待以上に頑張ってきました。2016年1月、この全国大会で最高賞である「文部科学大臣賞」を福井県の生徒が受賞し、みんなで喜び合いました。それだけに、全国大会の中止決定は大変ショックでした。大人の事情で中止になったことを生徒に伝えることはできませんでした。「何とかして、全国大会をできないものだろうか。」 堺市長あての開催要望書も作成しました。しかし、予算がついていない状況では開催は難しいと理解しました。しかし、中止にするわけにはいかない。生徒を裏切ることはできない。「堺ができないなら、福井でやるしかない。福井で全国大会を開催しよう!」となったわけです。
私はこれまで7年間、県立美術館を所管する県文化振興課に出向していました。福井の未来を担う芸術家を育成する趣旨なら、福井県の支援を受けて、全国大会を福井で開催できると思ったのです。しかし、開催までの道のりは思った以上に困難なことでした。会場をどこにするのか、審査員はどなたに頼むのか、経費はいくらかかるのか、スケジュールは大丈夫なのか。そもそも、このような福井の提案に賛同してくれる県があるのかどうかもわかりませんでした。不安なことが盛りだくさんの中で何度もギブアップしそうになりましたが、そんな時いつも目に浮かんだのが、全国を目指してきた美術部員の姿です。これまで堺で懇親を深めてきた先生方に相談し8月、ついに実行委員会を立ち上げました。
幸いなことに、福井県の共催を承認いただき、会場として福井県立美術館第1展示室をお借りできることができました。場所が決まり、次は審査員です。堺での全国大会で、当初から審査を務めてこられた東良雅人先生(前文科省視学官)に相談したところ、二つ返事で了解いただけました。福井県内からも、全国大会にふさわしい、芸術的に教育に理解のあるアーティストの皆様にお願いすることができました。雪の降る、福井の地で第1回を迎えることができ、コロナ禍ではありましたが多くの入賞生徒が家族とともに福井へおいでいただきました。
私は当時、小学校の校長を務めていましたが、美術教育における小中連携の一環として関係者の理解をいただき、この「アートの甲子園」事務局を引き受けました。審査には、本校体育館や会議室を使用しました。学校職員にもボランティアで手伝っていただき、作品の受付、保管や審査準備、多くの人に協力いただきながら、準備を進めました。準備をする1月~3月は、福井は大雪となることもあり、「沖縄から作品が届くだろうか」「審査員の先生方は大雪で来られるだろうか」と心配することもありました。また、中学校の先生方は、進学業務(入試対応)や卒業への準備もあり、全国展の準備業務は困難を極めました。一般のボランティアも募り、何とか開催をし、連日多くの皆様に観覧いただきました。最終日の表彰式には、遠く沖縄県からも生徒や保護者、先生方がご出席いただき、全国大会を実施してよかったと強く感じました。
他地区での開催を検討いただきましたが、経費や会場借用について課題は多く、快く引き受けていただく地区事務局は見つかりませんでした。これでもう中止にするしかないと思いました。しかし、「今年の全国大会はどこですか? 福井ですか?」といった福井県の生徒の声を聞き、生徒は今年も全国大会を期待していることにハッとしました。生徒の期待を裏切りたくない、その一心で今回のWEB展開催に至りました。
テーマは、「中3の今は、この今しかない。」です。本展覧会では、大人には描けない、中学生の今にしか描けない絵。今の中学生の心の声が聞こえてくるような絵を大切にしたいと思いました。ただ、今回はWEB展での開催です。こうした中学生の声がWEBで伝わるのかどうか、不安でした。
WEB展を開催し、しばらく経ちました。スマホやタブレット、パソコン等で毎日のように作品を見ることができます。すると、何回か見ていると見え方が変わってくることに気づきました。また、日に日に「いいね投票」も増えてきて、私のよいと感じている絵と重なったり、逆に違っていたりします。ただ、作品を見るだけでなく、「いいね投票」をすることでWEB展に参加している気持ちになります。
考えてみれば、美術の授業における鑑賞活動も、モニターやプロジェクター、教科書や資料集、最近ではタブレットで作品を見て取り組んでいいます。本物を見ることが一番と思いつつも現実的にはできないことも多くあります。今回は展覧会場での展示ではありませんが、より多くの人に、より身近に鑑賞できるWEB展になっているように思います。審査講評には、これまでも審査にご協力いただいてきた東良雅人氏等にもご厚意でお手伝いいただきました。先生方の温かいお言葉が生徒の自信につながることを願っています。
このWEB展を通して、全国の美術部員がお互いの作品に刺激を受け、新たな制作へ向け、その意欲を高めることができればと感じています。野球選手で言えば、イチロー選手(愛工大名電)がかつて松井秀喜選手(星稜高)を中学生のときから意識していたように、もしかしたら、このWEB展でライバルが見つかるかもしれませんね。将来進学した美術大学で同じ仲間になり再会することもあるでしょう。また、顧問の先生方も、全国の美術部の交流を通じて、時代における美術部の課題について考えることができるのではと思います。従来は毎日のように活動していた美術部も、今では週に2~3回しか実施できない学校や土日の活動は禁止されている場合もあると聞きました。部活動の地域移行が進む中、美術部の未来にも大きな課題が見えてきています。絵を描きたい生徒にとって「学校の美術室」はとても大切な場所です。そうした場所が地域に果たしてできるでしょうか。運動部系の体育館と同様に美術部にとっての居心地のよい「美術室」のような場所を地域につくっていくことも、これからは考えていくべきなのでしょう。
さらに、これまで美術の授業や美術部で生まれた作品は、豊かな学校文化を創ってきたはずです。美術教育が豊かな学校文化を創る一助となり、よりよい美術の授業づくりにつながってきたのではないかと感じています。このような活動を通して、中学校における美術教育の意義をあらためて考えていければと思います。今後とも、皆様方のご支援、ご協力をお願いし、全国の中学生による「アートの甲子園」を継続していきたいと思います。
来年度こそは、是非、美術館等での開催を実現させましょう。
先ずは全国の美術部を対象としたコンクールが福井の先生方のお力で継続できていることに心から敬意を表したいと思います。作品の傾向として、自分の中学校生活を振り返り、そして未来に期待する姿を描いた作品に佳作が多かったように思います。きっと急速に変化し、予測不能な現代社会を敏感に反映しているのでしょう。また、審査方法の変更に伴い立体作品が参加できた意義は大きく、今後の展開が楽しみです。
全国中学生アートの甲子園も今回で4回目となりました。私は第1回から審査や講評をしていますが、いつも大切にしていることは「その作品に中学生の“今”はあるか」です。確かに表現のテクニックが素晴らし作品も沢山ありますが、それはこれから先にも続いていくものです。しかし、中学生の時期だからこと感じられることや考えられることは“今”しかないのです。今回も沢山の素晴らしい“今”に出会うことが出来ました。今回応募された皆さんがこれから進む人生の中で、その時期その時期の“今”を大切にして自分自身を成長させたり、見る人に感動を与えたりする表現が生まれていくことを心から願っています。
出品作品全体からは、大人顔負けの発想力、それを形にする強さを感じました。目の前にある現実、心象をそのまま信じ表現する前向きの力は、見る方にも希望を届けてくれます。また思いもよらぬ心情を追求した、深みのある表現にも出会えました。その意味で大変勉強になりました。実物を想像しながらの審査でしたが、実物を前にすると、サイズ感やテクスチャなどから受ける印象が変化するかもしれませんが、いずれにせよ、優れた作品群であることに間違いはありません。このような企画に参加させていただきましたこと、心より感謝申し上げます。
例年の通り、自分の内面に向き合い悩みや希望等を主題として、それぞれ独自の表現方法をとことん追求した質の高い作品がそろいました。立体表現も、素材や加工する技能の多様性が進展しており、今後のさらなる新しい表現の工夫にも期待がもてました。一方デザイン作品が少なかった印象で、今後絵画造形の表現に負けない秀逸な作品を期待したいと思います。
中学校生活や自分の好きなもの、何気ない日常や風景などから発想して制作し、中学生らしい夢や希望、現実、悩みなどを織り交ぜた素晴らしい作品が出品されていました。テーマに基づき独自の表現がなされたものや画面構成がしっかりした作品が多かったと思います。今後も多様な素材を用いた立体やコラージュ、色彩や筆致等へのこだわりを持った平面など、テーマに沿いながら新たな挑戦をしていってください。
大きな画面に描くことは大変難しいのだが、部分と全体のバランスを崩さず描き上げるその構成力に驚きました。画面が広い分、いろいろな色が細かく使え、華やかな画面がつくれていました。反対に、埼玉県 川越市 城南中学校の共同作品「幸せを摘む」など、柿渋の独特の色合いだけで構成された立体作品も大変魅力的でした。色数を絞ってテーマに迫る絵画作品もあり、可能性を感じました。
いつも審査員をしていて不思議に思うことがあります。それは、「描いている本人を描いた作品」「制服を着ている自分を描いている作品」が多いということです。これは、初めに先生か学校からのテーマとして、「自分自身をみつめて、答えをだしてください。」って言われているのかなと思います。
私は(一回、描かなくてもいいし、描いてもいいけど)なんとなく、そこに違和感を覚えています。絵を描くことは本来、自由であってほしいと思っています。自由の意味からすると、制服って真反対に思っています。だから、その枠組みを一旦外してみたらどうでしょうか。そうすることで、抜ける解放と開放があることを感じてほしい。絵を描くって、そういうことだと思うのです。
じっくりと取り組んだ力作ぞろいでした。緻密に描きこんだ作品にも惹かれますが、発想の豊かさや個性的な表現の作品に、中学生時代ならではの粗削りな面白さを感じます。立体作品もみられ、今後も様々な描画材や素材を利用して、表現の幅を広げていってほしいと思います。自分自身をテーマにした自画像的な作品も多く、取り組む過程で何度も自分自身と対話したことと思います。これからも自分らしい表現を追求していってください。
全体的に絵のレベルが高くて驚きましたが、大切なのはその画力をどう使うか。上手さに拘るあまり、メッセージ性が隠れてしまっている作品も多く感じました。「大人に褒められたい」が全面に出ている作品も見られました。当たり障りのない絵より、個人の爆発が私は見たいです。作風を確立させて書き続ければ、画力は勝手に付いてくるものだと思うので、エネルギーの迸る作品を期待します。
全体的に描写力が高い作品が多くありました。緻密にリアルに描写するその一歩先にある、自分らしい表現を見つけられると、より自分の思いや描く世界が見るものに伝わってくると思います。ひたすら「足し算」するだけでなく、ちょっと「引き算」してみることも楽しんでみてください。
審査を集計すると、上位に選ばれない絵の中にも、魅力的で個性的な作品が多くあります。審査は本当に難しいといつも感じています。中学生の皆さんには、是非、賞をねらうのではなく、自分が好きなテーマで自由にとことん描く姿勢を大切にしてほしいと思うのです。
また、いろんな機会を大切にし、多様な刺激を受けてほしいと思います。教科書にあるゴッホやピカソ、モネだけでなく、村上隆や奈良美智、名和晃平など、まさに今を生きて制作している芸術家にも関心をもってほしい。美術館やギャラリー、あるいはコンサートホールや伝統文化施設等へも積極的に出かけ、本物を見る目を育ててください。来年、新しい表現に挑戦する皆さんと作品をとおして再会できることを楽しみにしています。